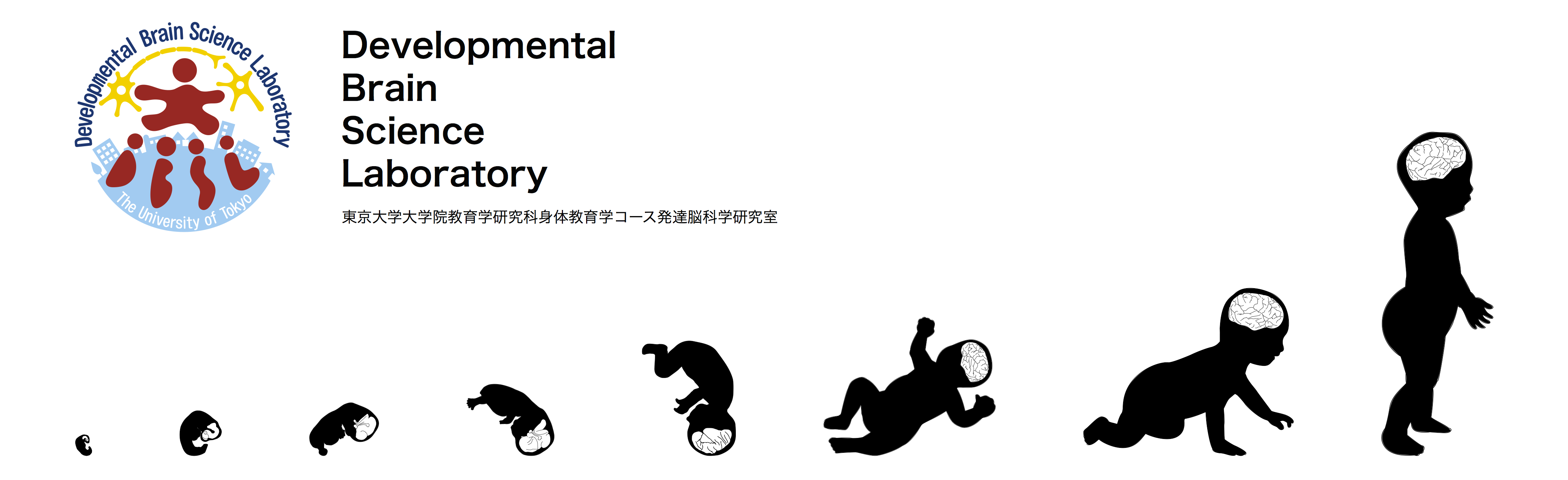2016年6月20日(月)の15:00より工学部12号館408号室(浅野キャンパス)にて、駒木文保先生(東京大学大学院情報理工学研究科)をお招きして、生体認証や個性に関する研究等に関してお話をしていただきます。ご専門は、理論統計の研究(情報幾何の視点からの予測理論の研究など),ベイズ理論,時系列・時空間データの解析,ネットワーク型の統計モデルなどです。ご関心のある方はどなたでもご参加ください。事前の連絡は不要です。
#本セミナーは、発達保育実践政策学センター主催の第3回発達基礎科学セミナーです。